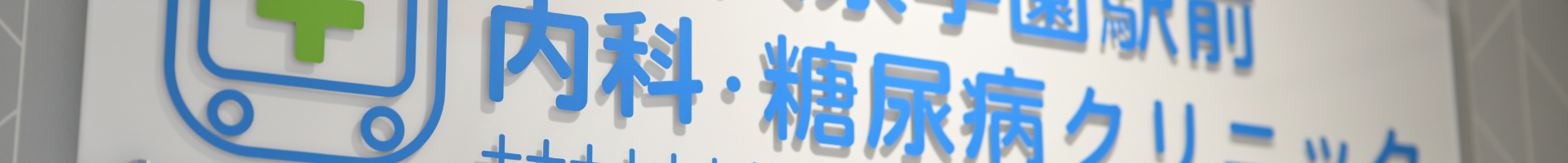
甲状腺疾患(バセドウ病・橋本病)
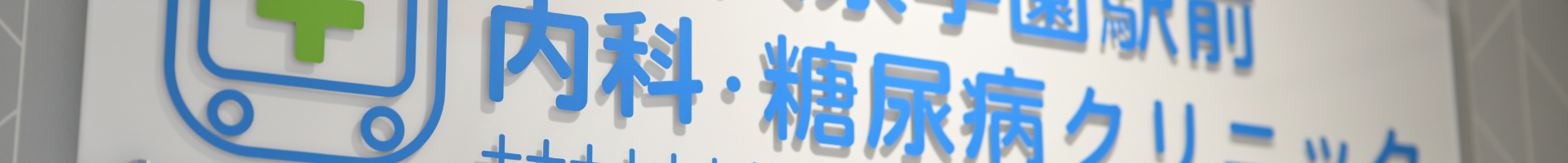
甲状腺疾患(バセドウ病・橋本病)

バセドウ病は、甲状腺を異常に刺激する物質(TSHレセプター抗体)が体内で生成され、この物質が甲状腺ホルモンを過剰に産生してしまう病気です。これによって代謝が高まる(亢進する)ことで様々な症状が現れます。バセドウ病は女性に多い病気で、男女比は男性1人に対して女性4人程度と言われています。年齢別では20歳台~30歳台の発症が多いですが、70歳台~80歳台で発症する方もいらっしゃいます。わが国の患者数は10万人程度と推定されており、決して珍しい病気ではありません。
バセドウ病は、自分の体を守るための仕組みである“免疫”が、甲状腺に反応してしまうことで起こる病気です。本来であれば外部からのウイルスや細菌などに対抗するための免疫システムに何らかの異常が起こり、甲状腺を刺激する「自己抗体」(TSHレセプター抗体:TRAb)ができてしまうため、甲状腺が常に刺激を受け、際限なく甲状腺ホルモンが作られ、過剰な状態(甲状腺機能亢進症)になってしまいます。
この自己抗体が作られてしまう原因は詳しくは分かっておらず、遺伝的なものに加えて、ストレスや過労などの環境要因が関わっていると考えられています。また妊娠や出産といった体内環境が大きく変化するタイミングで発症する例もありますので、いつもと少し違うなと思ったら、しっかりと検査を受けて適切な治療を受けていただくことが大切です。
バセドウ病の診断では以下の検査を行い、結果を総合的に判断したうえで診断します。
治療は大きく分けて、薬物療法、アイソトープ療法(放射性ヨウ素内用療法)、手術療法(甲状腺摘出術)の3つがあります。多くの場合、まず、抗甲状腺薬による薬物療法が行われます。薬物療法を2年以上継続しても薬を中止できる目途が立たない場合には、アイソトープ療法や甲状腺摘出術などの他の治療法を検討します。
抗甲状腺薬という薬を定期的に服用し、甲状腺ホルモンの合成を抑えることで、過剰となっている血液中の甲状腺ホルモンの量を正常にする治療です。薬を飲み続けるだけで治療ができますが、治療が長期間となり(治療が必要なくなるまでに2~3年かかることが多いです)、再発する場合もあります。また、稀ですが重篤な副作用が起こる場合もあります。抗甲状腺薬の副作用として、発疹、かゆみ、肝機能障害などがあります。また、ごく稀ではありますが無顆粒球症といって、放っておくと命にかかわるような副作用が起こることもあります。抗甲状腺薬を開始してから最初の3か月は特にまめな定期受診が必要で、2週間ごとの通院と血液検査を受けることが大切です。
抗甲状腺薬による治療の効き目が芳しくない場合や、副作用が強く出てしまう場合に選択されることがある治療法です。放射線を出す性質をもったヨウ素(放射性ヨード)のカプセルを飲むことで甲状腺の細胞を破壊し、甲状腺ホルモンの分泌量を抑えます。抗甲状腺薬と比べて治療期間が短期間であり、再発も少ない治療法ですが、放射性ヨードによる甲状腺細胞の破壊は長期間続くため、将来的には逆に甲状腺機能低下症の状態になり、今度は甲状腺ホルモン製剤を飲み続けなくてはいけなくなります。妊娠中・妊娠の可能性のある患者さま、授乳中の患者さまには行うことができません。
甲状腺を全部(全摘術)または一部を残して(亜全摘術)切除する治療法です。特に甲状腺の腫れがひどい場合や、抗甲状腺薬による効き目が芳しくない場合、副作用が強く出てしまう場合に選択されます。アイソトープ療法と同様、抗甲状腺薬治療よりも短期間での治療が可能であり、全摘出術の場合は再発はありませんが、将来的に甲状腺機能低下症を引き起こしてしまうリスクがあります。また外科的な治療のため、のどに小さな傷が残ります。
橋本病は慢性甲状腺炎とも呼ばれる甲状腺機能低下症の代表的な病気です。免疫の異常により甲状腺に炎症が生じ、甲状腺が少しずつ破壊されます。甲状腺の炎症により首が太くなったように感じます。甲状腺の機能が下がると全身の代謝が低下するため、耐寒性の低下、体重増加、体温低下、だるさ、便秘、高脂血症などが出現します。また、気分が落ち込んだり、不安感が増したりすることもあります。うつ病や更年期障害、脂質異常症として治療されていることもあるので、疑わしい症状があれば、甲状腺ホルモンの検査をおすすめします。橋本病は女性に多い病気で、男女比は男性1人に対して女性20人程度、年齢は30歳台~50歳台の方が多くいらっしゃいます。橋本病を引き起こす原因となる自己抗体は一般成人女性の10人に1人といった非常に高い頻度で見つかることが言われています。
橋本病は、自分の体を守るための仕組みである“免疫”が、甲状腺に反応してしまうことで起こる自己免疫疾患です。本来であれば外部からのウイルスや細菌などに対抗するための免疫システムに何らかの異常が起こり、甲状腺を攻撃する「自己抗体」(抗サイログロブリン抗体:TgAb、抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体:TPOAb)ができてしまい、甲状腺に炎症を引き起こします。この状態が長く続くと甲状腺ホルモンが作れなくなってしまい、甲状腺機能低下症に至ることがあります(甲状腺の炎症が慢性的に続くことから、「慢性甲状腺炎」とも呼ばれます)。
橋本病の診断では以下の検査を行い、結果を総合的に判断したうえで診断します。
甲状腺機能が正常であれば治療の必要はありません。機能が低下している場合には、基本的に足りない甲状腺ホルモンを補充する薬物療法を行います。