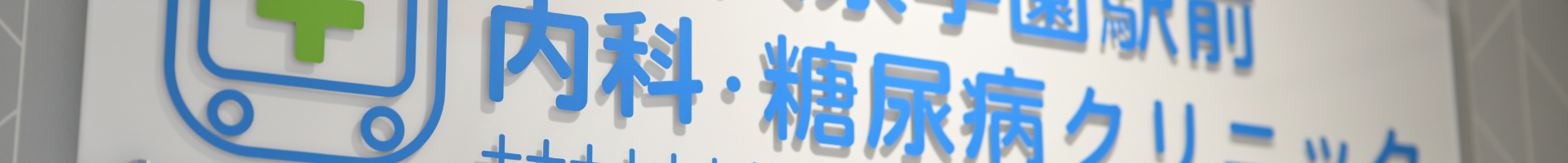
糖尿病とは
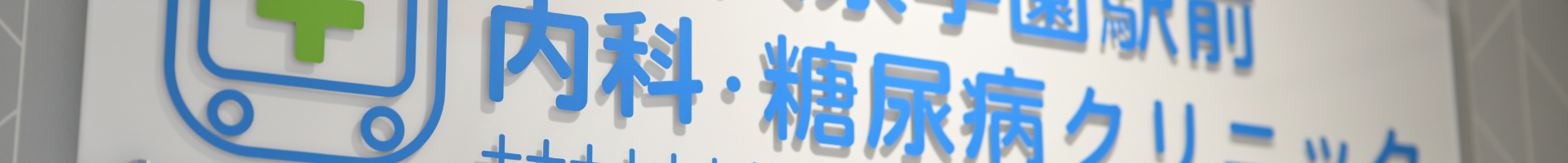
糖尿病とは

糖尿病とは、インスリンというホルモンの働きが悪くなることで、血液中のブドウ糖濃度(血糖値)が慢性的に高くなる病気です。私たちの体は、食事から摂取したブドウ糖をエネルギー源として利用しています。このとき、膵臓から分泌される「インスリン」が、血液中のブドウ糖を細胞に取り込む手助けをします。しかし、インスリンの分泌量が減ったり(インスリン分泌低下)、分泌されても正常に機能しなくなったりする(インスリン抵抗性)と、ブドウ糖が細胞に取り込まれず血液中に溢れてしまい、高血糖状態が続いてしまうのです。これが糖尿病の基本的なメカニズムです。糖尿病は、その原因によって主に以下のタイプに分類されます。
自己免疫などにより膵臓のインスリンを作る細胞が破壊され、インスリンがほとんど分泌されなくなるタイプ。
主に自己免疫(自分の体を守るはずの免疫が、誤って自分自身の細胞を攻撃してしまうこと)によって、膵臓にあるインスリンを作る細胞が破壊されてしまうことが原因です。なぜ自己免疫が起こるのか、はっきりとした理由はまだ完全にはわかっていません。
細胞が破壊されるため、インスリンが体内でほとんど、あるいは全く作れなくなります。そのため、血糖値を下げる唯一のホルモンであるインスリンが絶対的に不足します。
子どもや若年層(30歳未満)での発症が多い傾向がありますが、成人や高齢者になってから発症することもあります。生活習慣とは直接関係なく発症します。
体内でインスリンを作れないため、インスリン注射(またはインスリンポンプ)によって体外からインスリンを補充する治療が必須です。血糖自己測定を行いながら、食事や運動量に合わせてインスリン量を調整していくことが基本となります。
遺伝的な要因に加え、過食や運動不足などの生活習慣が原因で、インスリンの効きが悪くなったり、分泌量が減ったりするタイプ。日本の糖尿病患者の9割以上を占めます。
インスリンが出にくい、または効きにくいといった遺伝的な体質(要因)を持っている人が、過食、高脂肪食、運動不足、肥満、ストレスといった生活習慣の乱れ(環境要因)にさらされることで発症します。
インスリンの分泌量が減ってしまったり(インスリン分泌不全)、分泌はされていてもインスリンがうまく働かない状態(インスリン抵抗性)になったりすることで、血糖値が高くなります。
中高年(40歳以上)での発症が多いですが、近年は食生活の欧米化や運動不足などにより、若年層でも増えています。
治療の基本は食事療法と運動療法です。生活習慣の改善だけで血糖コントロールが良好になる場合もあります。 これらで不十分な場合は、薬物療法(飲み薬(経口血糖降下薬)や、インスリン注射、GLP-1受容体作動薬(注射薬)など)を併用します。
妊娠すると、胎盤からインスリンの働きを妨げるホルモンが分泌されるため、インスリンが効きにくく(インスリン抵抗性)なります。通常は膵臓がインスリン分泌を増やして対応しますが、それが追いつかない場合に血糖値が高くなります。
妊娠中に初めて発見または発症した、糖尿病には至っていない糖代謝異常(高血糖)のことを指します。(※妊娠前から糖尿病だった場合や、妊娠中に診断された明らかな糖尿病は含みません)
母体や胎児への影響を避けるため、厳格な血糖コントロールが必要です。基本は食事療法(適切なカロリー摂取と栄養バランス、分割食など)です。食事療法だけで不十分な場合は、胎盤を通らず胎児への影響が少ないインスリン注射が用いられます。(飲み薬は原則として使用しません)(補足)産後は血糖値が正常に戻ることが多いですが、将来的に本格的な2型糖尿病を発症するリスクが高いため、産後も定期的な検診が必要です。
当院は練馬区・大泉学園のかかりつけ医として常に最新の知見に基づき診療を行っております。健康診断で異常を指摘された方、糖尿病の症状が認められる方、他院で治療中だが転院を検討されている方などお気軽にご相談ください。
糖尿病の初期は自覚症状がほとんどなく、静かに進行するため「サイレントキラー」とも呼ばれます。 健康診断などで「血糖値が高い」と指摘されて初めて気づくケースも少なくありません。
しかし、高血糖状態が続くと、次のような症状が現れることがあります。
高血糖は全身の血管を傷つけ、特に細い血管が集中する部分に深刻なダメージを与えます。これを三大合併症と呼び、糖尿病治療の最大の目標はこれらの予防です。
目の網膜の血管が傷つき、視力低下やかすみを引き起こします。最悪の場合、失明に至ることもあります。
腎臓のフィルター機能を持つ毛細血管がダメージを受け、老廃物をろ過できなくなります。進行すると人工透析が必要になります。
手足の末梢神経が障害され、「しびれ」「痛み」「感覚が鈍くなる」などの症状が現れます。足の感覚が麻痺すると、怪我に気づかず壊疽(えそ)を起こし、切断に至る危険もあります。
自己免疫反応の異常などが引き金となり、自身の免疫細胞が誤って膵臓のβ細胞(インスリンを作る細胞)を攻撃・破壊してしまうことが主な原因です。生活習慣とは直接関係なく、突然発症することが多いのが特徴です。
2型糖尿病は、複数の要因が絡み合って発症します。
家族に糖尿病の人がいると、体質的に糖尿病になりやすい傾向があります。
肥満につながり、インスリンの効きを悪くします(インスリン抵抗性)。
エネルギー消費が減り、インスリン抵抗性を助長します。
インスリンの働きを妨げる悪玉物質を分泌します。
10時間以上食事を摂らずに測定。基準値を超えていると糖尿病が疑われます。
食事時間に関係なく測定した血糖値。
赤血球中のヘモグロビンが、どれくらいの割合でブドウ糖と結合しているかを示す数値です。過去1〜2ヶ月の平均血糖値を反映するため、血糖コントロール状態を把握する上で非常に重要な指標となります。
糖尿病の治療の基本は「食事療法」「運動療法」「薬物療法」の三本柱です。
年齢、性別、活動量に応じたカロリーを守る。
炭水化物、タンパク質、脂質、ビタミン、ミネラルをバランス良く摂る。
「野菜・きのこ類(食物繊維)」→「肉・魚(タンパク質)」→「ごはん(炭水化物)」の順で食べると、血糖値の急上昇を抑えられます。
1日3食、決まった時間に食べることで血糖の変動を安定させます。
ウォーキング、ジョギング、水泳など。ブドウ糖や脂肪の燃焼を促し、血糖値を下げます。
週に3〜5日、1回20〜60分程度を目安に、無理なく続けられる運動を選びましょう。
患者さんの病状や体質に応じて、最適なお薬を処方します。血糖値を下げるお薬(例:スルホニルウレア薬、ビグアナイド薬)、インスリン感受性を改善するお薬(例:チアゾリジン薬)、インクレチン作用を利用したお薬(例:GLP-1受容体作動薬、DPP-4阻害薬)などを使用します。薬物療法の効果や副作用に関しては、定期的に患者さんと共に評価し、適切な治療の継続・調整を行います。
糖尿病は長期的な管理が必要な疾患です。当クリニックでは、患者さんが継続的なケアを受けられるよう、定期的な受診や血糖値・HbA1cの測定を推奨します。また、患者さんの症状や治療効果の変化に応じて、治療方針を柔軟に見直し、適切なケアを提供します。
専門医として、血糖値のコントロールが難しい方や、専門的な治療が必要な方の診療はもちろん、地域のかかりつけ医として「糖尿病かもしれない」と初めて指摘された方にも安心してお越しいただきたいと思っています。「専門の先生はちょっと怖そう」「生活習慣について厳しく指摘されるのでは」と不安に思われる方も、いらっしゃるかもしれません。しかし、糖尿病は早い段階から適切な治療を始めることで、合併症の進行を抑え、健康寿命(自立して健康に過ごせる期間)を延ばすことが目指せるため「早く治療を開始しておけば良かった・・・。」そういった後悔を後々されないためにも一度お越しいただきたいと思っております。どんな些細なことでも、気軽にご相談いただければと思います。敷居が高いと思わず、まずは一度いらしてください。